望遠鏡の焦点距離を短くすると____が大きくなる。
a) 視野
b) 倍率
c) 収差
d) 重量
答え: a) 視野
説明: 焦点距離が短いと視野が広くなり、より広い範囲を観測できます。
驚いた点: 焦点距離が短いだけで視野が広がるなんて、光学のシンプルさに驚きました。
ニュートン式望遠鏡では主鏡の光を____鏡で反射して観測する。
a) 平面
b) 凹面
c) 凸面
d) 非球面
答え: a) 平面
説明: ニュートン式では主鏡(凹面)の光を平面の副鏡で接眼部に導きます。
驚いた点: 平面鏡で光を曲げるなんて、設計の工夫に驚きました。
カセグレン式望遠鏡の特徴は____が長いことである。
a) 焦点距離
b) 鏡の直径
c) レンズの厚さ
d) 架台の高さ
答え: a) 焦点距離
説明: カセグレン式は副鏡で光を折り返し、長い焦点距離をコンパクトに実現します。
驚いた点: 小さくても焦点距離が長いなんて、コンパクトさに驚きました。
望遠鏡の集光力を決めるのは主鏡の____である。
a) 面積
b) 厚さ
c) 材質
d) 曲率
答え: a) 面積
説明: 主鏡の面積が大きいほど、より多くの光を集められます。
驚いた点: 面積だけで集光力が決まるなんて、単純な仕組みに驚きました。
天体望遠鏡の倍率は対物レンズの焦点距離を____レンズの焦点距離で割った値である。
a) 接眼
b) 平面
c) 補正
d) 非球面
答え: a) 接眼
説明: 倍率 = 対物レンズ焦点距離 ÷ 接眼レンズ焦点距離 で計算されます。
驚いた点: 倍率がこんな簡単な計算で出るなんて、数式の分かりやすさに驚きました。
電波望遠鏡の代表例として____がある。
a) アレシボ
b) ハッブル
c) ケック
d) ヤーキス
答え: a) アレシボ
説明: アレシボ電波望遠鏡はプエルトリコにあった大規模な電波望遠鏡です。
驚いた点: アレシボがこんな有名なんて、電波望遠鏡の存在感に驚きました。
望遠鏡の視野を広くするために使われるのは____望遠鏡である。
a) シュミット
b) ニュートン
c) ガリレオ
d) カセグレン
答え: a) シュミット
説明: シュミット式は広い視野を持ち、星図作成などに適しています。
驚いた点: 視野を広くする望遠鏡があるなんて、用途の違いに驚きました。
X線望遠鏡の例として____が知られている。
a) チャンドラ
b) ケック
c) VLT
d) MMT
答え: a) チャンドラ
説明: チャンドラX線観測衛星はX線を観測する宇宙望遠鏡です。
驚いた点: X線専用の望遠鏡があるなんて、観測の多様性に驚きました。
赤外線望遠鏡の例として____がある。
a) スピッツァー
b) アレシボ
c) ヤーキス
d) フッカー
答え: a) スピッツァー
説明: スピッツァー宇宙望遠鏡は赤外線で宇宙を観測しました。
驚いた点: 赤外線で見る望遠鏡があるなんて、別の視点に驚きました。
太陽観測に特化した望遠鏡は____望遠鏡と呼ばれる。
a) 太陽
b) 電波
c) X線
d) ガンマ線
答え: a) 太陽
説明: 太陽望遠鏡は太陽の表面や活動を観測するために設計されています。
驚いた点: 太陽だけを見る望遠鏡があるなんて、専門性に驚きました。
望遠鏡の架台の一種である赤道儀は地球の____に合わせて動く。
a) 自転
b) 公転
c) 傾き
d) 磁場
答え: a) 自転
説明: 赤道儀は地球の自転に同期して天体を追尾します。
驚いた点: 地球の自転に合わせるなんて、動きの調和に驚きました。
望遠鏡の分解能を向上させるには____を大きくする必要がある。
a) 口径
b) 焦点距離
c) レンズ厚
d) 架台高
答え: a) 口径
説明: 口径が大きいほど回折限界が小さくなり、分解能が向上します。
驚いた点: 口径が分解能に直結するなんて、大きさの重要性に驚きました。
ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は主に____線で観測する。
a) 赤外
b) 可視光
c) 紫外
d) X線
答え: a) 赤外
説明: JWSTは赤外線で遠方の銀河や星形成を観測します。
驚いた点: 赤外線で遠くを見るなんて、新しい技術に驚きました。
望遠鏡の光学系で球面収差を補正するレンズは____レンズである。
a) 非球面
b) 平面
c) 凸
d) 凹
答え: a) 非球面
説明: 非球面レンズは球面収差を軽減し、像を鮮明にします。
驚いた点: 非球面で収差が減るなんて、レンズの形に驚きました。
重力波を観測する望遠鏡の一例は____である。
a) LIGO
b) HST
c) VLT
d) JWST
答え: a) LIGO
説明: LIGOはレーザー干渉計を用いて重力波を観測します。
驚いた点: 重力波まで見えるなんて、望遠鏡の進化に驚きました。
望遠鏡の接眼レンズを交換すると____が変わる。
a) 倍率
b) 集光力
c) 解像度
d) 視野角
答え: a) 倍率
説明: 接眼レンズの焦点距離で倍率が変わります。
驚いた点: レンズ交換で倍率が変わるなんて、手軽さに驚きました。
天文台で使われる巨大望遠鏡の鏡は通常____製である。
a) ガラス
b) 金属
c) プラスチック
d) セラミック
答え: a) ガラス
説明: ガラスは熱膨張が少なく、精密な鏡面に適しています。
驚いた点: ガラスがこんな大事なんて、素材の選択に驚きました。
望遠鏡の視野が狭くなる原因は____が長いことである。
a) 焦点距離
b) 口径
c) レンズ厚
d) 架台高
答え: a) 焦点距離
説明: 焦点距離が長いと倍率が上がり、視野が狭まります。
驚いた点: 焦点距離で視野が変わるなんて、設計の影響に驚きました。
望遠鏡の設計でコマ収差が発生するのは____鏡が原因である。
a) 球面
b) 平面
c) 非球面
d) 凸面
答え: a) 球面
説明: 球面鏡は光軸から外れた光でコマ収差を生じます。
驚いた点: 球面だと収差が出るなんて、鏡の形の難しさに驚きました。
超大型望遠鏡VLTは____にある。
a) チリ
b) アメリカ
c) 日本
d) ヨーロッパ
答え: a) チリ
説明: VLT(Very Large Telescope)はチリのアタカマ砂漠に設置されています。
驚いた点: チリにこんな大きな望遠鏡があるなんて、場所の意外性に驚きました。
望遠鏡の光学系で像面湾曲を補正するのは____レンズである。
a) フィールドフラットナー
b) 色消し
c) 非球面
d) 平面
答え: a) フィールドフラットナー
説明: フィールドフラットナーは像面を平坦化し、周辺部の歪みを補正します。
驚いた点: 像面を平らにするレンズがあるなんて、補正の技術に驚きました。
天体観測で星雲を観測するのに適した望遠鏡は____望遠鏡である。
a) 反射
b) 屈折
c) 電波
d) X線
答え: a) 反射
説明: 反射望遠鏡は大口径で集光力が高く、淡い星雲の観測に適します。
驚いた点: 星雲に反射がいいなんて、集光力の大事さに驚きました。
望遠鏡の分解能の理論限界を決めるのは光の____である。
a) 波長
b) 強度
c) 速度
d) 偏光
答え: a) 波長
説明: 分解能は波長と口径に依存し、波長が短いほど分解能が上がります。
驚いた点: 波長で分解能が変わるなんて、光の性質に驚きました。
宇宙背景放射を観測する望遠鏡の例は____である。
a) COBE
b) HST
c) VLT
d) MMT
答え: a) COBE
説明: COBE(宇宙背景探査機)はマイクロ波で宇宙背景放射を観測しました。
驚いた点: 宇宙の始まりをマイクロ波で見るなんて、発想に驚きました。
望遠鏡の主鏡を冷却するのは____を減らすためである。
a) 熱雑音
b) 色収差
c) 球面収差
d) コマ収差
答え: a) 熱雑音
説明: 赤外線望遠鏡などでは熱雑音を抑えるため、主鏡を冷却します。
驚いた点: 冷却で雑音が減るなんて、観測の工夫に驚きました。
焦点距離が短い望遠鏡の特徴はどれですか?
a) 狭い視野
b) 高い倍率
c) 広い視野
d) 重い架台
答え: c) 広い視野
説明: 焦点距離が短いと視野が広がり、広範囲の観測が可能です。
驚いた点: 短いだけで視野が広いなんて、光学の効果に驚きました。
ニュートン式望遠鏡に使われる副鏡はどれですか?
a) 平面鏡
b) 凹面鏡
c) 凸面鏡
d) 非球面鏡
答え: a) 平面鏡
説明: 平面鏡が主鏡の光を側面の接眼部に反射します。
驚いた点: 平面鏡がこんな役割なんて、シンプルな仕組みに驚きました。
カセグレン式望遠鏡の利点はどれですか?
a) 小型で長い焦点距離
b) 色収差が少ない
c) 広い視野
d) 軽量化
答え: a) 小型で長い焦点距離
説明: 光を折り返す設計で、コンパクトに長い焦点距離を実現します。
驚いた点: 小さくても高性能なんて、設計の賢さに驚きました。
望遠鏡の集光力に最も影響するのはどれですか?
a) 主鏡の面積
b) 焦点距離
c) レンズの厚さ
d) 架台の種類
答え: a) 主鏡の面積
説明: 面積が大きいほど多くの光を集め、暗い天体も観測できます。
驚いた点: 面積が光の量を決めるなんて、基本的な力に驚きました。
倍率を変更する方法はどれですか?
a) 主鏡を交換
b) 接眼レンズを交換
c) 架台を調整
d) レンズを磨く
答え: b) 接眼レンズを交換
説明: 接眼レンズの焦点距離を変えることで倍率が変わります。
驚いた点: レンズ交換で簡単に変わるなんて、手軽さに驚きました。
どの望遠鏡が電波を観測しますか?
a) アレシボ
b) ハッブル
c) ケック
d) ヤーキス
答え: a) アレシボ
説明: アレシボは電波望遠鏡として有名でした。
驚いた点: 電波で宇宙が見えるなんて、観測の幅に驚きました。
シュミット式望遠鏡が適しているのはどれですか?
a) 惑星観測
b) 星図作成
c) 太陽観測
d) ガンマ線観測
答え: b) 星図作成
説明: 広い視野で一度に多くの星を撮影できます。
驚いた点: 星図に特化してるなんて、目的の明確さに驚きました。
どの望遠鏡がX線を観測しますか?
a) チャンドラ
b) ケック
c) VLT
d) MMT
答え: a) チャンドラ
説明: チャンドラはX線専用の宇宙望遠鏡です。
驚いた点: X線に特化した望遠鏡があるなんて、専門性に驚きました。
赤外線観測に使われる望遠鏡はどれですか?
a) スピッツァー
b) アレシボ
c) ヤーキス
d) フッカー
答え: a) スピッツァー
説明: スピッツァーは赤外線で星形成や銀河を観測しました。
驚いた点: 赤外線で宇宙を見るなんて、視点の違いに驚きました。
太陽望遠鏡が観測するのはどれですか?
a) 太陽の表面
b) 遠方の銀河
c) 電波
d) 重力波
答え: a) 太陽の表面
説明: 太陽望遠鏡は太陽フレアや黒点を観測します。
驚いた点: 太陽だけに絞るなんて、焦点の明確さに驚きました。
赤道儀が追尾するのはどれですか?
a) 地球の自転
b) 太陽の動き
c) 月の軌道
d) 風の方向
答え: a) 地球の自転
説明: 地球の自転に合わせて天体を追尾します。
驚いた点: 自転にピッタリ合うなんて、精密さに驚きました。
分解能を向上させる要因はどれですか?
a) 大きな口径
b) 長い焦点距離
c) 小さなレンズ
d) 軽い架台
答え: a) 大きな口径
説明: 口径が大きいほど回折限界が小さくなり、分解能が上がります。
驚いた点: 口径でこんなに変わるなんて、大きさの力に驚きました。
ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測対象はどれですか?
a) 赤外線
b) 可視光
c) 紫外線
d) 電波
答え: a) 赤外線
説明: JWSTは赤外線で初期宇宙や星形成を観測します。
驚いた点: 赤外線で過去が見えるなんて、技術の進化に驚きました。
球面収差を補正するのはどれですか?
a) 非球面レンズ
b) 平面レンズ
c) 凸レンズ
d) 凹レンズ
答え: a) 非球面レンズ
説明: 非球面形状で光の集まりを均一にします。
驚いた点: 形を変えるだけで収差が減るなんて、レンズの工夫に驚きました。
重力波を観測するのはどれですか?
a) LIGO
b) HST
c) VLT
d) JWST
答え: a) LIGO
説明: LIGOは重力波を検出する干渉計です。
驚いた点: 重力波を捉える装置があるなんて、科学の進歩に驚きました。
接眼レンズを交換する目的はどれですか?
a) 倍率の変更
b) 集光力の向上
c) 解像度の調整
d) 視野の狭小化
答え: a) 倍率の変更
説明: 焦点距離の異なる接眼レンズで倍率を調整します。
驚いた点: 交換するだけで倍率が変わるなんて、簡単さに驚きました。
主鏡に使われる材質はどれですか?
a) ガラス
b) プラスチック
c) 木材
d) 紙
答え: a) ガラス
説明: ガラスは熱変形が少なく、高精度な鏡面に適しています。
驚いた点: ガラスがベストなんて、身近な素材に驚きました。
焦点距離が長い望遠鏡の特徴はどれですか?
a) 狭い視野
b) 広い視野
c) 低い倍率
d) 軽量化
答え: a) 狭い視野
説明: 焦点距離が長いと倍率が上がり、視野が狭まります。
驚いた点: 長いと狭くなるなんて、視野の変化に驚きました。
コマ収差の原因はどれですか?
a) 球面鏡
b) 平面鏡
c) 非球面鏡
d) 凸面鏡
答え: a) 球面鏡
説明: 球面鏡は軸外光でコマ収差を引き起こします。
驚いた点: 球面だと問題が出るなんて、鏡の形の影響に驚きました。
VLTが設置されている場所はどれですか?
a) チリ
b) アメリカ
c) 日本
d) オーストラリア
答え: a) チリ
説明: VLTはチリのパラナル天文台にあります。
驚いた点: チリがこんな場所なんて、天文台の立地に驚きました。
像面湾曲を補正するのはどれですか?
a) フィールドフラットナー
b) 色消しレンズ
c) 非球面レンズ
d) 平面レンズ
答え: a) フィールドフラットナー
説明: 像面を平坦化し、周辺部の歪みを減らします。
驚いた点: 湾曲を直すレンズがあるなんて、補正の技術に驚きました。
星雲観測に適した望遠鏡はどれですか?
a) 反射望遠鏡
b) 屈折望遠鏡
c) 電波望遠鏡
d) X線望遠鏡
答え: a) 反射望遠鏡
説明: 大口径で集光力が高く、淡い星雲に適します。
驚いた点: 反射が星雲にいいなんて、集光力の強さに驚きました。
分解能に影響するのはどれですか?
a) 波長
b) レンズの厚さ
c) 架台の重さ
d) 観測時間
答え: a) 波長
説明: 波長が短いほど分解能が向上します。
驚いた点: 波長がこんなに大事なんて、光の細かさに驚きました。
宇宙背景放射を観測した望遠鏡はどれですか?
a) COBE
b) HST
c) VLT
d) MMT
答え: a) COBE
説明: COBEはマイクロ波で宇宙背景放射を測定しました。
驚いた点: 宇宙の過去をマイクロ波で見るなんて、観測の深さに驚きました。
主鏡を冷却する理由はどれですか?
a) 熱雑音の低減
b) 色収差の補正
c) 球面収差の防止
d) 重量の軽減
答え: a) 熱雑音の低減
説明: 赤外線観測では熱雑音を抑えるために冷却が必要です。
驚いた点: 冷却で観測が良くなるなんて、温度の影響に驚きました。


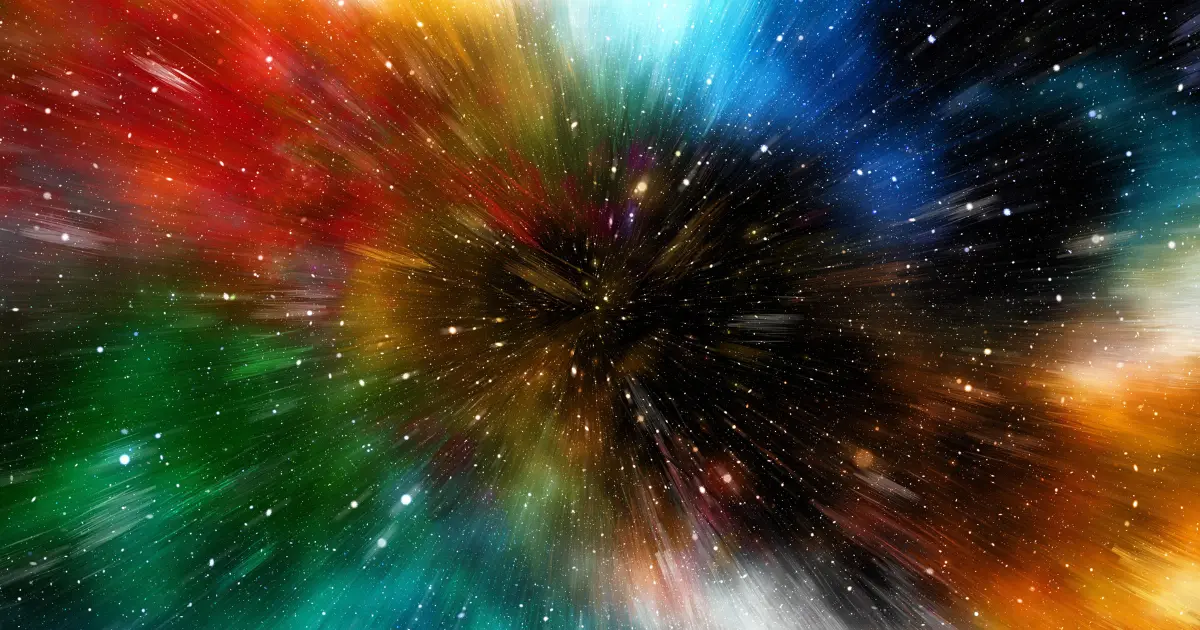




コメント